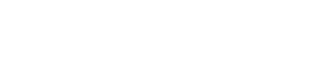interview
「電算印刷で働く人」にスポットをあてる特別インタビュー
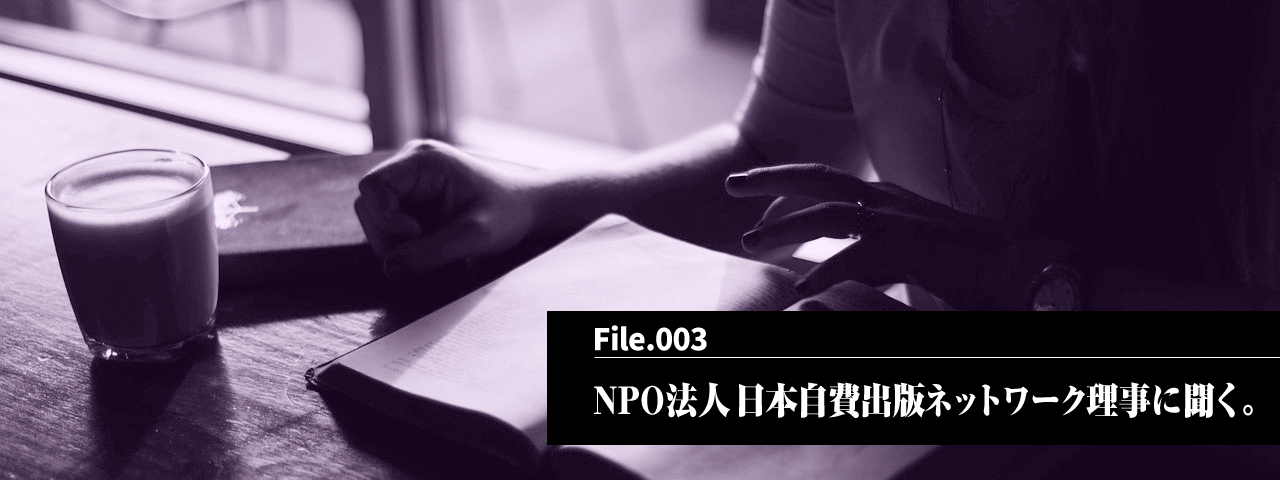
NPO法人 日本自費出版ネットワーク(代表理事・中山千夏)とは、日本全国で広く行われている自費出版を新しい民衆文化ととらえ、その普及を通じて学術、文化、芸術の振興と豊かな市民生活の創造を目指しています。そのため、自費出版物の作成にかかわるあらゆる活動を支援するとともに、インターネットなどを利用した自費出版情報の発信、流通、販売支援などを行い、多くの市民が自由に自己表現できる社会の実現を目的としているNPO法人です。
NPO法人 日本自費出版ネットワーク理事でもある、営業部 加藤洋子さんにお話を伺いました。
(2018年11月12日 公開)
――NPO法人日本自費出版ネットワーク公認の自費出版アドバイザーが在籍していますが、どんな資格なのですか。
- 加藤
-
「自費出版アドバイザー」とは、自費出版を希望する著者の方へ製作全体の適切なアドバイスを提供するエキスパートとして、NPO法人日本自費出版ネットワークが認定した資格です。
時には編集者、時にはディレクターであり、造本を含めた印刷 製作のみならず、著作権 肖像権などの知的財産権に関する知識も要求される「自費出版」の専門家といえます。
資格の取得には講座受講および試験があり、取得するためには2年の期間が必要となります。電算印刷㈱には4名の自費出版アドバイザーが在籍していますが、現在長野県ではこの4名のみとなります。
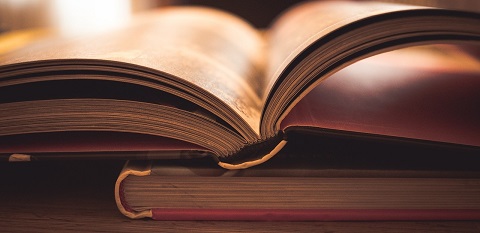
自費出版の一番の目的は「自分の想いや歴史を形に遺す」こと
――近年、ネット環境が充実して、電子書籍の普及などにより本離れ、本が売れない時代となっていますが、その中で自費出版の位置づけ、役割はどんなものでしょうか
- 加藤
-
自費出版の一番の目的は「自分の想いや歴史を形に遺す」ことではないでしょうか。
もちろん電子書籍による自費出版も一つの手法ではあります。けれど「遺す(後世に伝える)」という目的においては、日々刷新される情報の中でいつしか埋もれ、消えていく可能性は否めません。「本」という物体だからこそ後世に遺っていくことは、現存する様々な古書が証明しています。
本離れはインターネットの普及という理由だけではないでしょうね。余暇を楽しむ方法に読書以外の選択肢が増えたため、と私は思います。知的好奇心を満たすためにはインターネットも書籍も両方利用するというのが現代かと。
「自費出版」は“本離れ”とは異なる次元に位置していますので、表現の自由が確約されている限り「文化」として消えることはないと考えています。
――『自費出版』というワードから感じるイメージとして、作成するにはお金がかかる、しっかりした文章力がないとダメ、高齢者の方が多いなど少しマイナスのイメージがあるのですが、お問い合せいただくお客様はどのようなご質問が多いですか
- 加藤
-
一番多いのはやはり「費用」に対するお問い合わせです。その次は「著述」に関するものでしょうか。
自費出版のイメージの多くは「ハードカバーで立派な本」。そしてお客様の心配は「そんな立派な本に文章力が追いついていかれない」「高額な料金を請求されるかも知れない」。逆に超プラス思考の方は「印税でひと儲け」(笑)。
本の製作費用は「最低限必要な資材と作業の料金」を除けば、かなりアバウトではあります。例えば〈お客様がご自身で組版をして、校正の必要がない完全データでのご入稿の場合〉と〈記述があまり得意でないお客様には、取材中のお話を録音してリライトしたうえで組版、校正を複数回した場合〉という条件の差だけても大幅に費用が異なりますし、そこにモノクロかカラーかなどの刷色の数 印刷用紙 ページ数 部数 製本方法の条件が加わると、その組み合わせ次第で費用の差は複雑に変化します。お客様のご予算に合わせた仕様 製作 製本方法を提案するのもアドバイザーの役割といえるでしょう。
余談ですが「実は本は1冊から作ることができるのです」という話をさせていただくと皆さん非常に驚かれます。
――自費出版アドバイザーの方は、どんな相談、アドバイスをしてくれますか
- 加藤
- 上記でもお答えしましたように、ご予算に合わせた本づくりの提案はもちろんのこと、ご入稿いただいた原稿の整理と内容のチェックをしたうえで、記述の統一や禁止用語についてのアドバイス、引用 参考文献の取り扱い方法、著作権侵害の回避方法などをアドバイスしています。また、著作権については、著作者である新聞社や著作権協会、JASRACなどへの申請手続きの代行もしています。
――若年層向けなどの本づくりには、どんなものがありますか
- 加藤
-
写真がメインの、例えばブログ内にアップした料理のレシピや手芸品を1冊の本にまとめたもの、お子さんの成長の記録など、手軽に作成できる本をおすすめします。本のサイズについては、小部数ならばメモ帳サイズの可愛らしいものからA3判サイズまで、お客様のご希望に合わせて対応させていただいています。
そろそろ下火かも知れませんが、ZINEの製作もいかがでしょうか。
ご両親へのプレゼントとして1冊だけの「2XXX年 ○○家のできごと」というのも楽しいかも知れません。
著者の想いは千差万別、その表現のしかたも千差万別。
いかに著者の想いを汲み取りながら「形として遺す」か
――最後に本づくりは楽しいですか。日本自費出版ネットワーク理事としてまた自費出版アドバイザーとして本づくりの魅力を教えてください。
- 加藤
-
もともと本好きが高じて「本を作る仕事がしたい!」と、この業界に飛び込みましたから、いわば天職かと。縁あって日本自費出版文化賞専門選考委員、日本自費出版ネットワーク理事という役職をいただきました。
本づくりの魅力は「これしかない」というものではないところですかね。そしてご自身の「想い」という姿が見えないものを、「本」という姿に昇華する…これに尽きるのでないでしょぅか。
そんな著者の想いは千差万別、その表現のしかたも千差万別、そこに寄り添っていかに著者の想いを汲み取りながら「形として遺す」か、創造力を掻き立てられるのが自費出版アドバイザー。表現する手法のひとつでもある「自費出版」という文化を未来へ繋いでいくことがNPO法人日本自費出版ネットワークの使命でもあります。

(注)所属、経歴およびインタビュー内容はすべては、取材当時のものです。